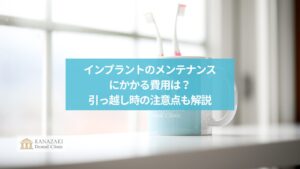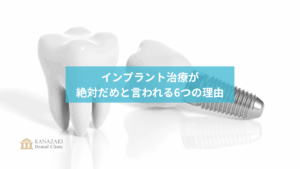インプラント治療は医療費控除の対象?
インプラント治療は医療費控除の対象です。そのため、1月1日から12月31日までに支払った治療費用の合計額が一定の条件を満たす場合、確定申告によって一部が還付されます。
なお、医療費控除とは、一定の条件を満たす医療費を所得から控除できる制度のことです。医療費控除を受ける際には、治療にかかった領収書や明細書が必要になります。2025年現在は電子明細や電子領収書も増えていますが、紛失や保存方法に注意しながら適切に保管・管理しましょう。
医療費控除が適用される条件
医療費控除が適用される条件は下記のとおりです。
- 1月1日~12月31日までに支払った医療費の合計額が10万円以上
- または、医療費の合計額が総所得金額等の5%以上
- 本人または生計を一にする配偶者・その他扶養親族の治療費であること
この「生計を一にする親族」には、6親等以内の血族や3親等以内の姻族なども含まれます(民法第725条)。したがって、ご自身以外でも該当範囲内の家族の医療費も合算して控除が受けられます。
インプラント治療における医療費控除の範囲
医療費控除の対象は、「治療を目的として支払った費用」です。インプラント本体の費用だけでなく、以下のような関連治療費や付随する費用も広く対象になります。
- CT検査費
- 骨造成手術費(サイナスリフトなど)
- 薬代(痛み止めや抗生物質など)
- 通院時の交通費(電車・バス・タクシー代など)
一方、下記のようなものは医療費控除の対象外となるケースが多いためご注意ください。
- 美容・審美目的でのインプラント(治療上の必要性がない場合)
- 通院時の駐車場代(公共交通機関が利用困難な地域で医師の指示がある等、特別な事情がない場合は原則対象外)
- 医療費とは直接関係のないサービス料(アフターケアでのクリーニング費用等のうち、美容目的と判断されるもの)
治療目的かどうかが判断のポイントになります。実費で支払った交通費・診断書費・薬代などは領収書や記録を残しておくようにしましょう。
ローン・クレジットカード払いでも医療費控除を受けられる
ローン(デンタルローン)やクレジットカードで支払った場合でも、医療費控除の対象になります。その際の支払時期の扱いは以下のとおりです。
- ローン(デンタルローン)の場合
→ 契約日の属する年の医療費としてカウント - クレジットカード払いの場合
→ カード会社への支払日ではなく、カードを利用した日(利用日)の属する年の医療費としてカウント
インプラント治療における医療費控除の計算方法
インプラント治療における医療費控除の対象額は、下記の計算式で求められます。
1年間にかかった医療費の総額-保険金などの補填金-10万円
補填金とは、健康保険や生命保険から支給されるものです。また、年収が200万円以下の場合は下記の計算式が適用されます。
1年間にかかった医療費の総額-保険金などの補填金-総所得の5%
年収別の還付金を計算
確定申告を行っても、医療費控除の対象額がすべてが還付されるわけではありません。還付金の割合(所得税率)は年収によって異なり、5〜45%となっています。

ここでは、年収別の還付金の目安を見てみましょう。なお、医療費の総額は50万円、補填金は0円と仮定し計算式に当てはめていきます。
年収200万円以下
医療費控除額=50万円ー0円ー10万円ー40万円
還付金=40万円✕5%=2万円
年収300万
医療費控除額=50万円ー0円ー10万円ー40万円
還付金=40万円✕10%=4万円
年収500万
医療費控除額=50万円ー0円ー10万円ー40万円
還付金=40万円✕30%=8万円
年収700万
医療費控除額=50万円ー0円ー10万円ー40万円
還付金=40万円✕23%=9.2万円
年収1000万
医療費控除額=50万円ー0円ー10万円ー40万円
還付金=40万円✕33%=13.2万円
インプラントの医療費控除を申請する方法
インプラントの医療費控除を申請するには、確定申告の手続きが必要です。必要書類を準備し、期間内に確定申告を行いましょう。
1.確定申告の必要書類を準備
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 給与所得の源泉徴収票
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知
確定申告書はA・Bの2種類があり、会社員の方はAを、個人事業主の方はBを準備します。国税庁のホームページでダウンロードできるほか、最寄りの税務署や役所でも入手できます。
源泉徴収票は会社から発行されるので、紛失しないよう大切に保管してください。
医療費控除の明細書は、領収書などに記載されている金額を入力し作成を進めます。こちらも国税庁のホームページに作成コーナーが設けられています。
医療費通知は、加入している健康保険組合から届きます。被保険者などの氏名・治療年月日や施設名・医療費額など、必要な情報が記載されているか必ず確認しましょう。
2.期間内に確定申告を済ませる
確定申告は期限が設けられています。原則として2月16日から3月15日までに手続きを済ませなければいけません。(日付が土曜・日曜・祝日だった場合は翌平日に繰り越されます。)
インターネット(e-Tax)でも申告できますが、手続きに関する質問や不安がある場合は税務署などで相談しながら進めるとよいでしょう。
3.年末調整では対応してもらえないので要注意
インプラントの医療費控除は、年末調整では対応してもらえません。年末調整で対象になるものは生命保険料控除や社会保険料控除、地震保険料控除などです。

マイナンバーカードを活用した電子申告(e-Tax)も活用しよう
1. e-Taxとは?
e-Tax(イータックス)とは、国税電子申告・納税システムのことで、インターネット経由で所得税や消費税、贈与税などの税金に関する申告を行える仕組みです。マイナンバーカードを利用してログイン・電子署名を行うことで、紙の書類に比べて提出手続きが大幅に簡略化され、受付から還付までのスピードが早まるメリットがあります。
2. 必要なものと初期準備
- マイナンバーカード
個人番号が記載されており、電子証明書が搭載されています。 - ICカードリーダーライター(パソコンで操作する場合)
マイナンバーカード内の電子証明書を読み取ります。
スマートフォンに対応したNFC機能を活用する方法もあります。 - パソコンまたはスマートフォン
e-TaxソフトやWebサイトにアクセスして申告書を作成します。 - マイナポータルとの連携(任意)
医療費通知情報や各種証明書を取り込み、入力を省略できます。
3. e-Taxのメリット
- 申告手続きがオンライン完結
税務署に行く必要がなく、24時間いつでも申告が可能です。 - 還付金の振り込みがスピーディ
紙の申告よりも審査が早く、3週間程度で還付金が振り込まれることが多いです。 - 添付書類の省略・自動入力
マイナポータルとの連携や医療費通知データの取り込みなど、書類の入力・添付を減らせます。 - 電子帳簿保存法への対応が容易
デジタルデータでの領収書管理が普及しており、適切な手続きであればそのまま申告に活用できます。
4. e-Taxによる医療費控除申告の流れ(概要)
- マイナポータル連携・医療費データの取得
加入する健康保険組合の医療費通知情報などを取り込みます。 - 医療費控除に必要な金額を入力(または自動入力)
インプラント治療の費用や関連検査費用などをまとめて入力。 - 還付金の振込先口座を登録
金融機関名、支店名、口座種別・番号などを入力。 - 電子署名・送信
マイナンバーカードを利用して本人確認・署名を行い、送信を完了。 - 受信通知を確認
送信後、受付結果や確認メッセージをチェックします。
スマホ申告で医療費控除の手続き
1. スマホ申告とは?
スマホ申告は、スマートフォン専用に最適化された確定申告手続きの総称で、国税庁が提供する「スマホ申告アプリ」やウェブブラウザから簡単に医療費控除・所得税の確定申告ができる仕組みです。マイナンバーカードをスマホのNFC機能で読み取り、e-Taxのシステムを利用してオンライン申告できます。
2. スマホ申告のメリット
-
- 24時間いつでも手軽に申告
アプリを立ち上げればすぐに作業でき、通勤時間や休憩時間などでも進められます。 - 紙の書類が不要・自動入力の充実
マイナポータルとの連携で、医療費や源泉徴収票の情報を自動入力できる場合があります。 - 領収書の撮影アップロード
紙の領収書をスマホのカメラで撮影し、金額を読み取って入力を簡易化する機能も拡充。 - 還付までの時間短縮
申告書がオンライン提出されるため、審査が早く、還付金もスムーズに振り込まれる傾向があります。
- 24時間いつでも手軽に申告
3. スマホ申告を行う準備
- マイナンバーカード対応のスマートフォン
… NFC機能(おサイフケータイなど)を使ってマイナンバーカードを読み取る。 - スマホ申告アプリまたはブラウザ
… 最新版をインストール、または国税庁のe-Taxサイトにアクセス。 - 暗証番号
… マイナンバーカードに登録した暗証番号を忘れずに用意。
4. スマホ申告の手順(概要)
- スマホアプリorブラウザにアクセス
→「確定申告書等作成コーナー(スマホ版)」に進む - マイナンバーカードでログイン
→ スマホのNFC機能にカードをかざして認証 - 必要情報の入力・医療費データ取り込み
→ 医療費通知や電子領収書があれば自動入力を活用 - 還付先口座の登録
→ 銀行口座情報などを入力 - 最終確認・送信
→ 入力漏れや金額のミスがないかチェックし、送信
電子領収書・電子明細の保存方法
改正電子帳簿保存法が2022年に施行され、電子明細や電子領収書での管理も一般的になっています。
ただし、以下の点に注意しましょう。
- 真実性の確保
- 改ざん防止措置などが必要
- 検索機能の確保
- 日付や金額などで検索できる状態にする
- 保存期間
- 原則として確定申告から5年間は保管(7年保管を推奨する場合も)
クラウドストレージや会計ソフトと連携して保管する場合も、国税庁の要件を満たしているかを必ず確認しましょう。
インプラントの医療費控除に関してよくある質問
インプラントの医療費控除に関して、よくある質問と回答をまとめました。
Q1. 無職や主婦でも医療費控除は受けられる?
A. 無職や主婦の方でも受けられます。以下のいずれかに該当する場合が多いです。
- 生活を一にする家族(扶養内)で医療費が10万円超
- 年度の途中で退職しており所得があった
- 年金所得や不動産所得・株式配当がある
Q2. デジタル領収書でも医療費控除の対象になる?
A. なります。ただし、電子帳簿保存法に則った形でデータを改ざん防止しつつ保管する必要があります。医療機関から電子データで発行された領収書は、そのまま保存システムに取り込むと便利です。
Q3. マイナンバーカードがないと医療費控除を受けられない?
A. マイナンバーカードがなくても受けられます。ただし、マイナンバーカードがあると、e-Taxでのオンライン申請が簡単になり、還付金も早く振り込まれるといったメリットがあります。
Q4. インプラントのメンテナンス費用も控除対象?
A. 治療目的で定期検診や治療継続中であれば、基本的に対象になります。単なる美容目的やクリーニングのみの費用は対象外と判断されることがあります。
担当医から「治療の一環」として証明される場合は、領収書を保管しておきましょう。
Q5. ふるさと納税と医療費控除は併用できる?
A. 併用可能です。ただし、医療費控除をするとふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなり、確定申告が必要になります。また、医療費控除額が大きくなるほど、ふるさと納税の控除限度額に影響が出る場合があります。
Q6. AIチャットボットやオンライン相談は利用できる?
A. 2025年現在、多くの税務署や自治体がAIチャットボットによる相談対応を行っています。国税庁のオンラインチャットサポートやビデオ通話相談なども導入されているため、電話や直接出向く手間を省けるケースが増えています。
まとめ
「確実に還付金を受け取るためには、期限内の申告と必要書類の不備がないことが大前提」です。以下のポイントをチェックしつつ、スムーズに医療費控除を行いましょう。
- インプラント治療費は医療費控除の対象となり、**関連費用(CT検査・骨造成・薬代・通院交通費など)**も含めて申請が可能です。
- 医療費が10万円以上(または総所得金額等の5%以上)かかった場合、翌年の2月16日~3月15日(日付が土曜・日曜・祝日だった場合は翌平日に繰り越し)に確定申告を行いましょう。
- 2025年現在、マイナンバーカードを活用したe-Taxやスマホ申告が主流となり、電子領収書やマイナポータルの情報連携を使えば手続きが大幅に簡略化されます。
- 電子帳簿保存法によりデジタル領収書の保存要件が定められているので、改ざん防止措置や検索機能を整えて保存することが大切です。
- 不安な場合は、AIチャットボットやオンライン相談を活用し、税務署や専門家に確認しながら進めると安心です。
インプラント治療でかかった費用について、医療費控除の還付金を受け取るには確定申告を行う必要があります。
確定申告は期限が決まっているので、その間に申告を済ませなければいけません。
申告に関して不明点などがある場合は、税務署で相談しながら進めれば安心です。確実に還付金を受け取るためにも、抜け漏れや必要書類の不備がないように注意しましょう。