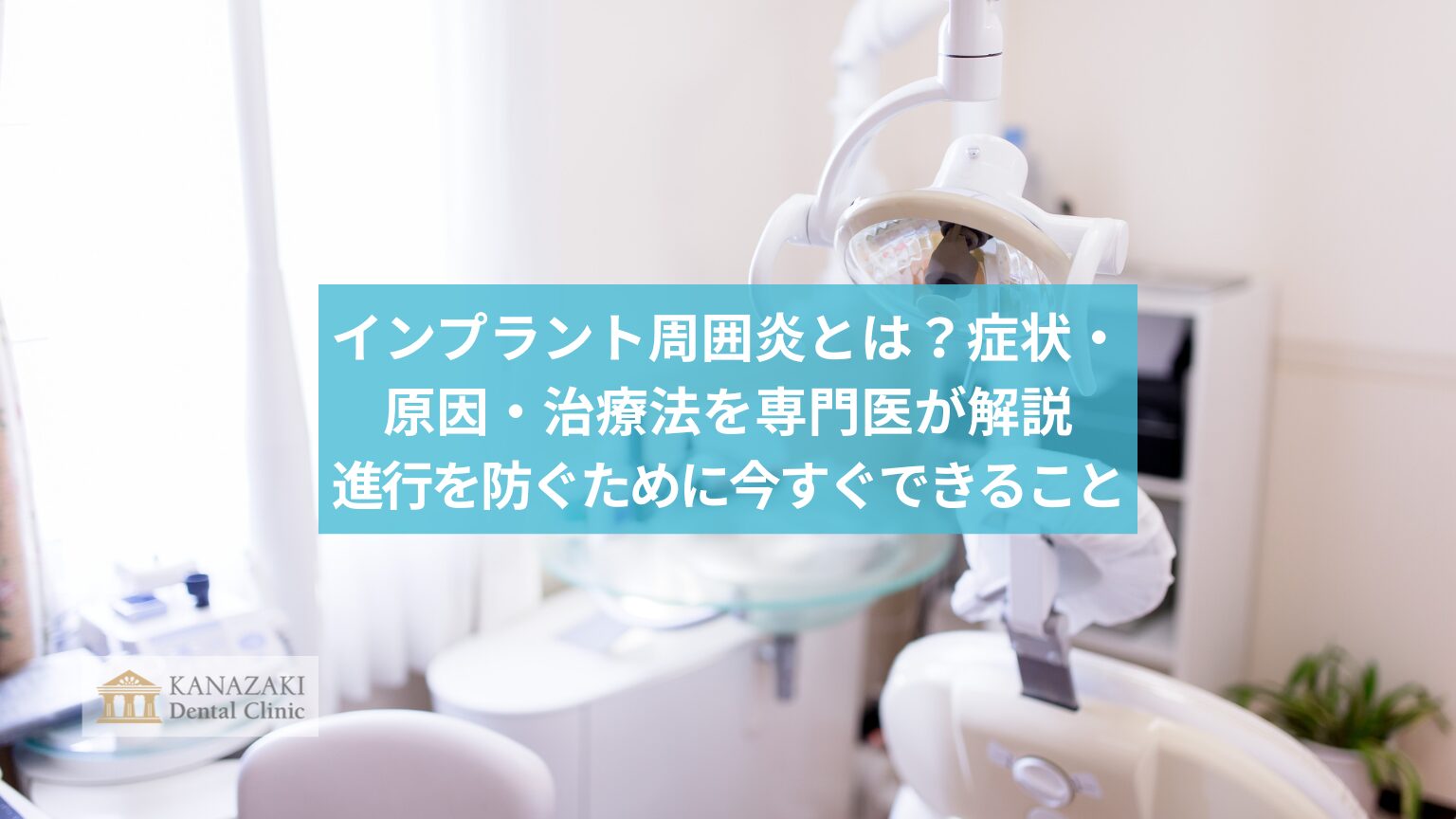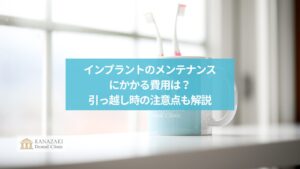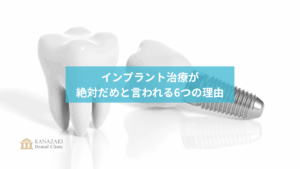インプラントの周囲が腫れたり、痛みや出血があると「インプラント周囲炎では?」と不安になりますよね。進行するとインプラントを失う可能性もあり、早期の対応が欠かせません。この記事では、数多くの周囲炎症例を治療してきたカナザキ歯科の金崎院長が、インプラント周囲炎の症状・原因・治療法をわかりやすく解説。再発予防のポイントまで専門的にお伝えします。
インプラント周囲炎とは?歯周病との違い

インプラント周囲炎とはどんな病気か
インプラント周囲炎とは、人工歯根であるインプラントの周囲に炎症が起き、歯茎や骨に悪影響を及ぼす病気です。天然歯における歯周病と似た進行様式を持ちますが、インプラントは天然の歯根膜がないため、一度感染が起きると急激に進行しやすいのが特徴です。炎症が続くとインプラントを支える骨(歯槽骨)が吸収され、最悪の場合はインプラントの脱落につながることもあります。
歯周病との違いとは
インプラント周囲炎と歯周病は、どちらも歯周組織の炎症ですが、構造的な違いがあります。天然歯には「歯根膜」というクッションのような組織があり、細菌の侵入をある程度ブロックできます。一方、インプラントにはこの歯根膜が存在しないため、防御機能が低く、細菌感染がダイレクトに骨へ広がりやすいのです。
また、歯周病であれば自然治癒の可能性がある初期段階でも、インプラント周囲炎は人工物が影響して進行が止まりにくく、専門的な介入が不可欠です。見た目や症状が似ていても、治療アプローチは大きく異なることを理解しておく必要があります。
放置したときのリスク
インプラント周囲炎を放置すると、インプラントを支える骨が破壊され、次第にぐらつきや脱落が起こります。インプラントは天然歯よりも強固に骨と結合していますが、一度骨吸収が進むと自然に回復することはありません。重度化すれば、外科的な再治療やインプラント撤去が必要になり、治療費や通院負担も増加します。
さらに、周囲の歯にも悪影響が及ぶ場合があり、結果として複数の部位にわたる再治療が必要になるケースもあります。そうなる前に、違和感や腫れを感じたら、早めに歯科医院を受診し、正確な診断を受けることが大切です。
周囲炎を疑うべき5つの症状チェック
歯茎の腫れ・出血
インプラント周囲炎の初期に最もよく見られる症状が、歯茎の腫れと出血です。特にブラッシング時やデンタルフロスの使用中に出血が見られる場合は、周囲の歯肉に炎症が起きている可能性があります。腫れは軽度であっても、放置すると骨にまで炎症が波及しやすく、早期の対応が求められます。
天然歯と異なり、インプラントでは自覚症状が現れにくいため、こうした微細な変化にも注意を払うことが重要です。見た目や違和感だけで判断せず、専門医の診断を受けましょう。
インプラントのぐらつきや違和感
インプラントは骨としっかり結合しているため、基本的に「ぐらつくこと」はありません。そのため、インプラントに違和感があったり、微妙に動いているような感覚がある場合は、周囲炎が進行している可能性が高いと考えられます。歯槽骨の吸収が始まり、インプラントを支える基盤が不安定になっているサインです。
ぐらつきを感じたら、すぐに歯科医院に相談することをおすすめします。早期発見であれば、外科処置を回避できるケースもあります。
口臭の悪化・痛みの出現
口臭の悪化もインプラント周囲炎のサインのひとつです。歯肉の奥に細菌が溜まり、膿が発生することで、独特の強い臭いが生じる場合があります。さらに、炎症が進むと患部に痛みや熱感が出ることもあり、進行性の感染症であることを示しています。
特に、普段よりも口臭が気になる、歯磨き後も改善しないといった状態が続く場合は、自己判断せず専門の診察を受けるべきです。
食事中の咀嚼時の不快感
インプラント周囲炎が進行すると、食事中の噛みごたえに違和感が出ることがあります。咀嚼する際にインプラント部位に圧がかかると、痛みや鈍い刺激がある場合は、骨の炎症や感染が進行しているサインといえます。
咀嚼の不快感は、インプラントそのものの問題だけでなく、かみ合わせのズレによる炎症促進も関与していることがあります。気になる場合は、精密検査を受けて根本原因を突き止めることが重要です。
インプラント部位の膿や熱感
膿の排出や局所の熱感は、感染が強くなっている兆候です。特にインプラント周囲から膿が出ている場合は、炎症が歯肉内の深部まで進行しており、骨の破壊が始まっている可能性も考えられます。こうした症状は自己ケアでは治まらず、専門的な洗浄や抗菌処置が必要になります。
少量でも膿が確認されたり、患部が熱を持っていると感じたら、すぐに歯科を受診しましょう。重症化を防ぐためにも、早期の対応が鍵となります。
原因は何?インプラント周囲炎の4大要因
プラークと歯石の蓄積
インプラント周囲炎の最大の原因は、口腔内に蓄積したプラーク(歯垢)や歯石です。これらには多数の細菌が存在し、炎症を引き起こす毒素を放出します。特にインプラントは天然歯と異なり、防御機構が弱いため、わずかなプラークでも急速に炎症が進行する傾向があります。
以下のような場合、注意が必要です
- 歯ブラシがインプラント周囲にしっかり届いていない
- フロスや歯間ブラシの使用が不十分
- メンテナンスを長期間受けていない
プラークは目に見えないことも多いため、自覚がなくても定期的なクリーニングが欠かせません。
咬合(かみ合わせ)と歯ぎしり
咬み合わせのバランスが崩れていると、インプラントに過剰な力が加わり、周囲の組織にダメージを与えます。特に夜間の歯ぎしりや食いしばりは無意識のうちに起きるため、骨や歯茎に持続的な圧力がかかり、炎症を助長する原因となります。
このような力の不均衡が続くと、インプラントの周囲に微細な損傷が生じ、細菌の侵入を許しやすい状態になります。ナイトガードの使用や、かみ合わせ調整などの対策が必要なケースもあります。
喫煙や糖尿病などの全身的因子
喫煙や糖尿病などの全身疾患も、インプラント周囲炎のリスクを高める大きな要因です。ニコチンは歯肉の血流を妨げ、免疫力を低下させるため、炎症の抑制が困難になります。また、糖尿病では高血糖が持続することで、傷の治癒が遅れ、細菌感染に対する抵抗力も低下します。
これらの要因を持つ方は、インプラント治療前からの全身管理と、治療後の継続的な健康管理が求められます。歯科医と内科医の連携が必要となる場合もあるため、医療機関での相談を忘れずに行いましょう。
不十分なセルフケアとメンテナンス不足
インプラントは人工物であるため、「虫歯にならないから大丈夫」と油断してしまう方がいますが、それは大きな誤解です。インプラントも周囲組織は天然の歯と同様に炎症を起こします。特に、歯間や歯周ポケットに汚れが残りやすいため、自己流のブラッシングだけでは清掃が不十分になるケースが多く見られます。
また、定期的な歯科でのメンテナンスを怠ると、初期の異常を見逃してしまい、進行した状態で気づくことになります。3ヵ月に1度のプロフェッショナルケアは、インプラントを長持ちさせるために不可欠です。
周囲炎でお悩みの方へ|カナザキ歯科無料相談の3つのメリット

ここまでご紹介したとおり、インプラント周囲炎は進行の早い疾患でありながら、早期に正しく対応すれば再発を防ぐことも可能です。特に、歯周病とインプラントの両方に精通した専門医に相談することで、治療の成功率や長期安定性は大きく向上します。
カナザキ歯科では、8,000本以上のインプラント治療実績や先進設備を活かし、患者様一人ひとりの体調・生活背景に配慮した「無理のない治療方針」を大切にしています。
「インプラントに違和感がある」「本当に治るのか不安」と感じた方は、まずは無料相談をご活用ください。ここでは、カナザキ歯科が提供する無料相談の3つのメリットをご紹介します。
違和感の早期対応が可能に
インプラント周囲炎は、早期発見・早期治療が鍵です。違和感や腫れ、出血といった初期症状を見逃すと、骨への感染が進行し、インプラント除去が必要になる場合もあります。
そのため、症状が軽いうちに専門的な診断を受けることが重要です。
カナザキ歯科では、「日本口腔インプラント学会専門医」「日本歯周病学会専門医」「日本顎咬合学会認定医」の資格を持つ歯科医師が在籍し、口腔全体の健康を総合的に診査します。歯周病とインプラント、両分野に精通しているからこそできる「根拠に基づいた治療計画」で、より安全で確実な処置を提供します。→お問い合わせバナー設置
他院治療中でも相談可能
「現在治療中だけど改善しない」「他院では断られた」といったお悩みも、ぜひご相談ください。
カナザキ歯科では、骨が足りない難症例や再治療にも数多く対応してきました。2025年7月時点で8,000本以上のインプラント治療実績があり、25年間無事故という高い安全性を誇ります。
院長をはじめとする専門チームが、患者様一人ひとりの状態・背景をふまえ、無理のない治療方針をご提案します。セカンドオピニオンとしての活用も歓迎しており、「実績ある先生の意見を聞きたい」という声にも誠実にお応えしています。
治療方針や費用もわかりやすく案内
無料相談では、インプラントに関するあらゆる不安や疑問に専門医が直接お答えします。愛媛県松山市にある当院では、メールによる無料相談を実施しており、現在も愛媛・高知・香川・広島といった中四国全域からご相談をいただいています。
無料相談を通じてご自身の症状や不安を明確にしたら、次に気になるのは「実際にどのような治療が行われるのか」ではないでしょうか。ここからは、カナザキ歯科がどのようにインプラント周囲炎に対して診断・治療・アフターケアを行っているのか、実際の医療体制と技術力をご紹介します。治療の流れや設備面の特徴を知っていただくことで、より安心してご相談いただけるはずです。
カナザキ歯科のインプラント周囲炎治療を解説
歯周病専門医による診断・処置
カナザキ歯科では、歯周病とインプラントの両分野における専門医が在籍しています。インプラント周囲炎は「インプラントの技術力」だけでなく、「歯周病への深い理解」が求められる治療領域です。当院では、「日本歯周病学会専門医」が口腔内全体を評価し、再発や炎症の原因を根本から見極めた上で治療を行います。
歯周病を正しくコントロールすることが、インプラントの長期的な安定につながるため、専門医による計画的な介入が何よりも重要です。
CT・Xガイドによる精密診断
当院では歯科用CTによる3D診断と、Xガイド(ナビゲーション手術システム)を用いた精密な治療計画を行っています。インプラント周囲炎の原因が「骨の形態」や「インプラントの埋入角度」にあるケースもあるため、画像診断の正確性が結果を左右します。
Xガイドを活用することで、0.1mm単位の微調整が可能になり、再治療や補綴修正の成功率を高めることができます。これらの先進機器を用いて、確実かつ安全な対応が可能です。
NKメソッド+ピエゾサージェリーの安全性
カナザキ歯科では、無事故25年という安全実績を支える独自の施術法「NKメソッド」を採用しています。これは、骨・粘膜の状態を的確に把握し、最小限の侵襲で最大限の成果を引き出す手術方法です。
さらに、骨を切削する際には「ピエゾサージェリー(超音波手術器)」を使用しており、神経や血管を傷つけるリスクを低減。これにより、難症例や再治療の場面でも患者様にとって安心な処置が可能となっています。
骨造成・再生療法など難症例にも対応
骨が少ない、インプラントが露出しているといった難症例にも当院は積極的に対応しています。骨造成や歯周組織再生療法といった高度な技術を用い、インプラントを支える土台そのものを再構築する治療も可能です。
以下のような治療が提供できます
- GBR(骨誘導再生療法)
- サイナスリフト・ソケットリフト
- 結合組織移植術(CTG)
- エムドゲインによる歯周再生
- 歯間乳頭再建術
これらの高度処置も、専門医の判断と豊富な経験により的確に選択・施行されています。
再発を防ぐアフターケア体制
治療が終わったあとも、インプラントの健康を維持するためには継続的なアフターケアが欠かせません。カナザキ歯科では、3ヵ月ごとのメンテナンスと年1回の歯科ドックを通じて、患者様の口腔環境を継続的に見守っています。
専用のインプラントクリーニング器具を使用し、セルフケアでは落としきれないバイオフィルムや歯石を除去。また、患者様の生活習慣や疾患リスクにも配慮しながら、再発を未然に防ぐプログラムを提供しています。
まとめ
インプラント周囲炎は、初期症状の見逃しから重度の骨吸収へと進行しやすい、注意が必要な疾患です。歯茎の腫れや出血、ぐらつき、口臭といったわずかなサインも、実は進行の入口である可能性があります。そのため、「気のせいかも」と思わず、早めに専門医へ相談することが重要です。
カナザキ歯科では、インプラントと歯周病、両方の専門医資格を持つ歯科医師が、25年間無事故・8,000本超の実績をもとに、患者様一人ひとりに合った安全で精密な治療を提供しています。先進設備と高度な技術だけでなく、患者様の生活背景まで考慮した「無理をしない治療提案」も当院の特徴です。
「もしかしてインプラント周囲炎かも」「今のままで大丈夫か不安」と感じた方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。専門医があなたの不安に丁寧にお応えし、必要な処置や予防の方法を一緒に考えさせていただきます。